Hi there.
続いて、日本実業出版より、教養としての「会計」入門を読み終わったので、感想という名の殴り書きをポストしておきます。
著者は、金子智郎さんで、元々ITエンジニアの公認会計士らしいです。異色の経歴。
そういえば、会計関係のポストを投稿するのは久々です。
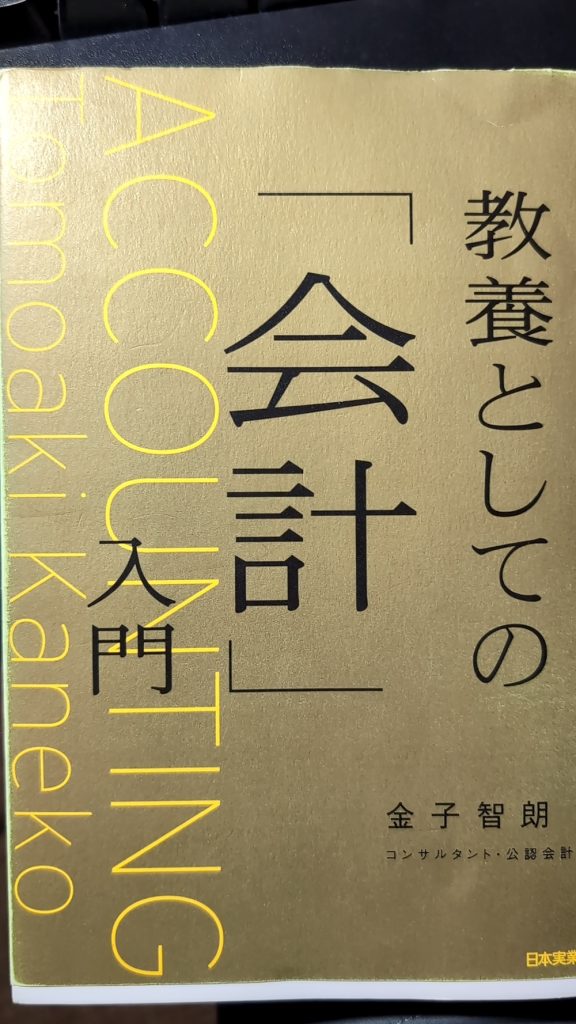
個人的におもしろかったとこ
最初のイントロダクションから興味深いお話があります。会計の歴史?みたいな逸話です。
世界初の株式会社である東インド会社と、その当時の決算書との関わりについて、の話は教養として面白いです。ここから「会計期間」の概念が生まれたってのもポイントです。
意外だったのは、近年、主要国のほとんどが IFRS を採用しつつあり、独自の会計基準を用いているのはもはやアメリカと日本ぐらいだったり。だったら早いとこ IFRS に切り替えればいいのに、とも思いますが、日本の偉い人?というか基準を制定する組織のあれやこれやも折に触れて話があります。
「財務諸表」は、金融商品取引法に出てくるもので、会社法では「計算書類」という単語が使われるっていうのは割と有名な話です。(会計勉強してれば)
あとついでに、「決算書」って単語は税法に出てくる単語だったようななかったような、記憶が曖昧ですけど。これらはほとんど同じような意味で、出典となってる法律が違うだけだったと思います。
フローとストックの考え方は、納得させられました。言い換えると、損益計算書は、会計期間における線の情報で、一方、貸借対照表は、期末時点における点の情報ってことです。
ちなみに、キャッシュ・フロー計算書は、もうそのまんまフローの視点ってことなんです。
日常用語の「価格」と会計用語の「価額」は厳密には意味が違うってことはぜひ覚えておきたいです。使い分け重要です。
貸借対照表は、めちゃくちゃ大まかにいうと、左側(借方)が資金の運用方法であり、右側(貸方)が資金の調達方法を意味するってことです。
「貸方」と「借方」を日本語訳したのは、福沢諭吉。という逸話は有名ですが、なんでこんな訳のわかんない訳になったのかのストーリーが書いてあります。この手のお話は刺さる人には刺さります。私は大好きです。
「貸借対照表は、上から順に流動性の順に並んでいる。」ってのは考えたこともなかったです。「流動資産」-> 「固定資産」の順はわかりやすいですが、なるほど、「負債」->「純資産」のような順になってます。
子会社たり得る基準は意外と形式基準ではなく、実質基準ってのは勉強になります。法律で決まってて機会的に定義されてるものだと思ってました。なるほどです〜
「会計というルールがどういうコンセプトでできているかという根本の部分を理解すること、が重要となる。」みたいなことが書いてありますが、これは全てに通じることですね、英単語や熟語でもいたずらに意味を覚えるのではなく、コアイメージや語源と一緒に覚えたほうが応用が聞いたりします。
著書内では、会計の一般原則のうち特に重要なものとして以下があげられていますが、
- 継続性の原則
- 資本取引・損益取引区分の原則
- 保守主義の原則
- 重要性の原則
財務諸表の理解で重要だと思ったのは、「完全無欠の財務諸表を作成することではなく、限られた時間や人的資源の中で、財務諸表が全体として企業の経済的実態を表すよう努めること」って考え方です。だからこそ会計はわかりづらいというか、そもそも厳格なルールというよりも意外と裁量が大きかったんですね。もちろん、それが故に会計監査という手続きが厳密に行われるんだろうとも思います。
損益計算書で重要な原則は次が挙げられていましたが、これらは全て日商簿記2級のテキストでも言及されています。(=それだけ重要ってことです。)
- 発生主義
- 実現主義
- 費用収益対応原則
個人的に覚えておきたいメモ:IFRS では、「収益」= “income” 、そのうち本業に関わる= “revenue”、本業外のもの= “gain”
売上原価は、英語では Cost of Goods Sold (COGS)
土地は、更地に戻せば基本的には元に戻るので、時間の経過や使用に伴う価値の劣化がないとも言える。とりもなおさず、資産価値を下落させる根拠がないってことですね。(=減価償却なし)あらためて理屈を説明されると、なるほど納得です。
減価償却には、キャッシュを社内に留保する効果がある。(費用としては計上されるがキャッシュ・アウトはないってこと)
「日本基準では、無権固定資産に計上したのれんを20年以内で償却するが、IFRS では償却しない。その代わりに、IFRS では、毎期厳格な減損の判定が求められる。」 ってのは知らなかったです。違いがあるとは知ってましたが、具体的にはこのような差異なんですね。
引当金が引当金たる要件、についてもなかなかおもしろかったです。簿記の試験受けるだけならこれとこれは引当金〜のように暗記するだけなので、そこのロジックの部分を知ることができるのは重宝します。
株式投資をするのであれば、第5章「経営分析のための財務指標」は必見です。ここでは、財務指標の数式とその意味を解説する月並みな本とは違い、それぞれの項をどのように解釈するのか、までのガイドラインが示してあり、財務指標の算出式の本質まで理解できます。
税金の分類についてあらためて見てみるとおもしろかったりします。
「担税者:税金を負担するもの」って単語は、日本語のボキャブラリとして知らなかったので、要暗記かなと。
ついでにいうと、税金や税制について説明する際の著者の当たりが若干キツい気がしますが、過去に税金絡みで何か嫌な思い出でもあったんでしょうか?
簿記の勉強をしていれば当たり前と言えば当たり前ですが、「利益を見てもキャッシュのことは何もわからない。」ってのは常に意識しておく必要があります。利益が出てる=お金があるって思ってしまいがちなので。
管理会計: Management Accounting
マネジメントの仕事=意思決定
また、管理会計の章では、言葉としては知っている、「逸失利益」や「機会費用」について、その本質を考えさせてくれます。
まとめ
さて、ザクザクっと気になった or おもしろかった部分について思いのままに書いてみましたが、全体的に、めちゃくちゃわかりやすい良著だと思います。
節ごとに挿入されているコラムも、とても有益な情報を提供してくれます。(経常利益って意外と日本特有の利益なんだよ〜とか)
日商簿記2級取得後かまたは、実務で経理関係の実績を数年積んで、財務諸表や会計処理についてある程度基礎知識がついた状態で読むと、「なぜそうなっているのか?」といった疑問を解決してくれます。
逆に言うと、全く会計について予備知識のない人にはお勧めしにくいです。と、いうことで、こちらの本を読む前に日商簿記2級を取得されることを強く強くお勧めします。
心理的なハードルや諸々の事情で、現実で実行するのはなかなか難しいことですが「保守性の原則(バッド・ニュースこそより早く正確に)」は、会計のみならずすべての企業活動に通ずる考え方ですね。確か Google の社内事情を紹介した本にも似たようなことが書いてあったはず。
折に触れて、日本の会計基準とIFRSの考え方の違いなどを対比的に説明してくれている部分がありがたいです。
また、「英語」の観点から、「厳密にいうと日本国内で使われている単語は誤訳だよね」みたいな話も出てくるので、英語好きの人間としては嬉しい限りです。
会計について資格勉強はしてみたけど、その本質の部分までは掴みきれていないかなぁ、って思ってる人向けの本かな、と思います。
さらにいえば、理屈理屈とした解説書ではなく、実際に事業で運用していく上で、現実の範囲内でいかに合理的な根拠をもとに会計という手続きを実行するのか?といった点に焦点を当ててある点も個人的に良かったです。
企業に求められているのは、完全無欠の財務諸表を作成することではありません。仕事はすべて、限られた人員と限られた時間、そして限られた予算の中でやっていますから、完全無欠の財務諸表を作成することなど、そもそも現実的に不可能なのです。
教養としての「会計」入門 p.118 ー 日本実業出版社
色々と会計関係の本は読んでますが、その中でもなかんずくおすすめなので、気になる人はぜひ手に取ってみてください。それでは。


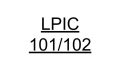
コメント