サム・アルトマンCEOが OpenAI から解任されたり何やら騒がしいですが、ちょろっと GPTs というサービスを触ってみたので、所感だけメモっておきます。
※11/20時点でMicrosoft社に引き込まれたとかどうとか、、、
個人的には、 Microsoft が発表してる Copilot Studio も気になります。この辺 GitHub で使われていた 「Copilot」がブランドとして使われる方針になるんでしょうか?
GPTs とは
GPTs とは、ざっくりいうと「各個人の好みで自由にカスタマイズされた chatGPT を作れる」ってサービスですね。もっと細かい話はオフィシャルブログに説明があります。
- コーディングなしで好みの GPT が作れる (chatGPTがウィザードみたいな役回りしてくれます)
- 11月中に GPT store なるものが展開されて、オリジナルの GPTs が売り買いできる
- “actions” を使って他のサービスと GPTs を連動させることができる(APIみたいなもの?)
- エンタープライズユーザは、「社内専用GPT」みたいなものをデプロイできる
と、まぁだいたいこんなとこですね。
※11月の3週目時点で急に有料版ユーザーが増えて負荷が高まったからってことで、新規の有料版登録が停止されてるみたいです。
とりあえず2個ぐらい作ってみました。

作り方は、chatGPT と会話して作ってく感じで、そこまで難しくないので割愛です。
ただし、2023年11月現在では、chatGPT 側の出力は英語のみになってました。(こちらからの入力は日本語でも解釈してくれます。)
使ってみた感じ
“English Conversation Partner” の方が結構面白い使い方できてます。
これは「フレンドリーな感じで対応して。文法的に致命的なミスがあれば指摘して。会話の練習がしたいので、長くても2〜3センテンスで返答するようにして。」みたいなプロンプトで設定してます。
これで、スマホアプリの方の chatGPT から、マルチモーダル機能(音声入力)使って、Podcast とかでよくわかんなかった単語を空耳で調べてもらう。ってのが個人的に今お気に入りの使い方です。
JapanTimes の「街に熊が出没しててどうとかこうとか」って文脈で、「マカーク」とか、「カブズ?カグズ?」とか結構わからない単語が出てきてたんですが、これを色々聞いてみてます。
“Do you know the name of the animal? Macaque.” とか音声入力してあげます。これは勝手に音声認識でうまく変換してくれてますね。ちなみに、これは「東南アジアとかに生息するオナガザル」のことです。日本人がイメージする猿が基本的にこれですね。てことは Monkey はもっと広く猿一般ってことですかね。もはや知らないと絶対わかんないレベルの単語語でしたが、一発で正解に辿り着きました。
続いて、「カブズ」って単語ですが、これは cabs とか cavs とか kags とか色々ありそうなので、文脈と共にマルチモーダル環境で聞いてみます。
“Do you know a good word for child bears, like cats or cags?” って音声入力してあげると、
“For baby bears, the term used is ‘cubs.’ Similarly, for cats, the young ones are called ‘kittens.’ Is there anything else you’d like to know about animals or their young ones?” って感じの返事が来ました。
「子熊については、”cubs” という単語が使われます。同様に、子猫は “kittens” と呼ばれます。他に何か、子供や若い動物について(英語で)知りたいことはありますか?」
もはや完璧ですね。ある程度英語ができる前提であればもう chatGPT だけで語彙力やら表現の拡張は問題ない気すらしてきます。ちなみに、cubs は肉食系の動物の子供(狼とか)に広く使われてる単語みたいです。
“Rust the Mentor” の方は普通に Rust のよくわかんない構文やらスニペットやらについて質問して使い倒してます。
この辺は記事に載せると Rust の説明の方がウエイトを占めてしまいそうなので割愛です。ライフタイムとか結構わかりにくい概念があるのでその辺の学習には助かってます。
思ったこと
最近のAI関連の発展で特に目覚ましいのが、トランスフォーマーに端を発する自然言語処理が異常なレベルで発展してるなってことです。
落合陽一さんの「英語が最強のプログラミング言語になりつつある」っていう言葉には納得させられてしまいます。
要するに、入力と出力のAPI(関数のシグネチャみたいなもの)と内部処理の仕様だけしっかり自然言語(特に英語)で記述できてしまえば、コーディングは機械がやる時代が来るんじゃないかなとも思えてしまいます。
こんなプロジェクトも動き出すぐらいに GitHub Copilot Workspace。
大きな時代の転換期なのかなと、おそらく、言語を用いたタスクがもっと気軽に行えるようになるのかなと思ってます。
人の移動するという身体機能が徒歩から馬、自転車、バイク、自動車、高速鉄道、飛行機なんて進化していき、東京-沖縄間がほんの2〜3時間で行き来できてしまうように、文章や絵を書いたりする機能も、筆、ワープロ、パソコン、AIって感じで機能拡張されてくのかなと。
人間の時間と能力は、文字や絵を描く「作業」ではなくてもっと抽象的でクリエイティブな部分に割けるようになる気もします。
ただし、どれだけ移動手段が発達しても、ウサイン・ボルトみたいに人類最速の人たちはもちろん必要であって、プログラミングや文章も、競技プログラミングやディベートとかの「人間枠」の競技としては残ってくかなと。
とりあえず、確実に時代は進歩しているのと楽しい時代には間違いないので、もっと色々試してみたいです。


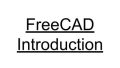
コメント