はい、ということで、LPIC 101/102 試験を受けてきました。
その辺りの勉強内容であったり、試験を受けるまでの流れとか防備のメモを残しておきます。
試験を受けるまで
試験の特性としては、暗記ゲームです。思考力を試すような問題はほとんどないと思ってOKです。
要するに、練習問題を周回させたもの勝ちなので、ある程度Linux を触ったことある人はテキストベースの学習はほぼ必要ないかなと思います。LPI 認定の公式問題集(白いやつ)と Ping-t で問題ひたすら解いておけば難なく合格できます。
会社や学校でまとめて受験申し込みしてくれるのでない限り、初見で受験の手続きするのはちょっとわかりにくかったです。(個人的に)
認定試験の母体が海外(カナダのトロント)なので、しょうがないのかなーとも思います。国内の IPA 情報技術者試験受けるみたいに、サクッと申し込みしてそのまま受験〜とはいかないです。
受験方法は主にオンラインも可能のようですが、カンニング防止でほぼ何もない部屋を用意しないといけなかったりとか、ちょっとめんどくさそうなのでだいたいの人はテストセンターで受けるかと思います。
受験方法の細かい説明をしているWebサイトはたくさんあるので、概要だけ。
テストセンターでの受験手順が大まかに以下の流れ:
- Linux Professional Institute (LPI) でアカウント(LPI ID) を作成する
- ピアソンVUE (試験の運営組織) で、 LPI ID を用いて試験予約、受験料支払い(Ping-t などのバウチャーも使えます)
- 試験を予約したテストセンターで受験
テストセンターで、身分証明書の提示が求められるためピアソンVUEの本人確認書類に関する説明をきちんと確認しておくこと。
2種類の本人確認書類が必要です。おそらく大半の人は以下でやるようになるかと、
- 運転免許証
- マイナンバーカードまたはクレジットカード
注意点はこんなものです。ちなみに試験当日は、受験する部屋の中への私物の持ち込みは基本的に不可なので、身分証明書だけ忘れなければ特に問題なく受験できます。
スマホはもちろん腕時計や筆記用具もロッカーに保管の上で受験となります。


101試験
101試験の範囲は明確に決まっていますが、だいたい、対OSで低レイヤーな内容となっています。
個別具体的な応用アプリケーションではなく、Linux のハードウェアやシステム設定など、とりあえず Linux システム自体を使えるようにするための内容が多いのかな、といった印象です。
コマンドや設定ファイルへの path なんかは英語ができればほぼ楽勝です。ただし、コマンドのオプション周りでちょっとわかりにくい。(というかだいぶ紛らわしいものがあるので要注意です)
私は Debian ユーザーなので、パッケージ管理に rpm, yum, zypper を使うことがないので、ここはやっぱり苦手でした。おそらくここで1問ミスしてるような。
vi のコマンド問題もそこそこ出てきますが、基本的なコマンドだけなので、毎日使ってれば楽勝です。
逆に、ブートローダーやパーティション周りは、Linux を使い始めるタイミングで設定したらそんなにいつもいつも触るものでも無いので、結構忘れてる部分が多いかと思います。重点的に復習要です。
60問で持ち時間90分ですが、しっかり勉強してれば30分もかからないです。サクッと終わりました。
102試験
102試験は、ネットワークやロギングなどの管理タスクが含まれていて、若干応用的なイメージです。
普段から Linux を触っていればシェル関係は特に問題ないと思います。反面、X11周りのユーザインターフェースやネットワーク設定など、だいたい自動で設定してくれるものは割と見直して暗記する内容が多いかと。
また、一回設定すればそれ以降はそんなに触ったりしないような設定項目もあるので、この辺りも要確認ですね。
個人的には、Network Manager 関係とか苦手でした、(Debian ユーザなので)Red Hat 系のツールに触れるタイミングがそんなにないんですよね。仕事で使うわけでもなく。
と、いうわけで、案の定ユーザインターフェースとデスクトップ周りの問題と、ネットワーク関連でミスしてますね。9割超えたかったんですが、まぁこんなもんでしょう。
102についてもそれなりに準備してれば、試験当日悩むような問題も特にないです。30分前後で解き終わります。
まとめ
まとめとしては、日常的に Linux 触ってる人からすれば簡単な部類に入ります。極端に難しい問題とかは出題されないです。
1点気になったのは、問題のオリジナルの言語が英語なので仕方がない面もあるとは思いますが、ちょっと日本語訳が雑(というか個人的に誤訳と思う)な問題がたまに出題されます。
「grep コマンドである一定の文字列を除くにはどうするか?」みたいな問題で、原文が “filter out” なんですけど、「除く」って書いてあったら普通に “-v” オプションを想定しちゃいます。日本語的には、「ある文字列を取り出す」と表現した方が適切なような。
あと、おそらく日本語と英語の句読点の使い方の違いだと思いますが、紛らわしいところで句読点が抜けてたりして「え???」てなることがありました。
結局、問題は日本語で出題されますが、英語の原文も確認しようと思えば試験の際に表示できるので、英語ができる人は原文で確認してみた方が正しく問題が解釈できるでしょうね。
類似の試験で LinuC というものがありますが、こちらは運営母体が日本の組織なので、上記みたいなことはきっと無いでしょう。

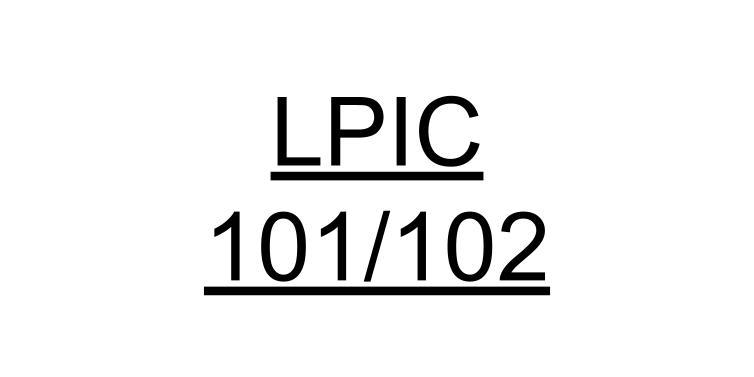

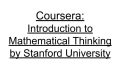
コメント